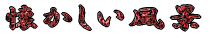 |
お正月を迎える心


|
お正月を間近に控えた年の瀬の年中行事の一つとして、今はほとんど見られない餅つきの風景がある。
明け方まだ暗いうちから一家総出で行う餅つきは、現代のように電動の機械で手軽につくのではなく、杵と臼でつくので、年末にはどこの家からも「ペッタンペッタン」と今では懐かしい音が流れていた。むしろを敷かれた土間には、どっしりと重い臼がすえられ、何段も重ねられたセイロで餅米が蒸され、杵で餅をつくのは力のある男衆・若い衆、臼取りをするのは一家の主婦を中心とする女衆、餅を丸めるのは子供も加わって、家族総出で、あるいは嫁いだ娘の家族や分家した一家も集まって賑やかに行われたのが、昭和30年代頃の餅搗き風景であった。
つかれた餅は、全部丸めてしまわずに、モロビタに何枚かにのして、伸し餅として保存され、切り餅にして焼いて食べた。搗きたての暖かく柔らかい餅は、あずき餅・大根おろし餅・きなこ餅としてその場でみんなに振舞われた。
みんなで食べた暖かくやわらかい餅の味は、賑やかなもち搗き風景とともに、現代の中高年世代の郷愁とも言えるものではないだろうか
大晦日に一家でそばを食べて、その年の家族の息災を感謝し、来る年の健康を祈願するという慣わしは、現代にも受け継がれている行事と言えよう
湯気のなか ちちははの在り 餅筵
父母、祖父母、叔父など大家族で餅屋さんほど搗ついた昔を時々思い出します。
年末の三十、三十一日は大掃除、二十九日は苦餅を嫌い二十八日には朝からてんてこ舞いの忙しさでした。かきもち、あられは大寒に入り旧正月の餅と一緒に搗きました。たっぷりの大根おろしで食べる搗きたて餅は格別です。
明日はいよいよお正月という大晦日は、一家が夜明かしをしてハレの日を待った。夜の12時になると方々の寺社から除夜の鐘が聞こえてきた。その響きを子供心に厳粛に受け止め、昨日までとは全てが新しく清新な空気がみなぎった特別な日が「元旦」であった。
前日までに家中のすす払い、大掃除などが済まされて家の内外は清められ、元日の朝は下着から普段着ている着物まで真っ更なものに着替えさせられた。昨年1年間使っていた食器類(茶碗や箸など)や歯ブラシなどの日用品なども新しいものと取りかえた。年神様(お正月様)を祀るために普段の神棚とは別に新しい神棚がしつらえられ、床の間には天神様の掛け軸がかけられ、御神酒・丸い大きな鏡餅などのお供えが三宝にのせて供えられ、これにダイダイ・ウラジロ・ユズリ葉・コンブ・干し柿などが添えられた。
正月15五日の「鏡開き」の日に、家族や地区の人たち(寺社の氏子など)と「ぜんざい会」を開き、細かく切った鏡餅を共に味わうのが慣例となっていた。
続く正月の25日には、学問の神様として崇拝される菅原道真公の命日、つまり天神講には焼きガレイが供えられた。
神に供えた餅などには神霊が宿る神聖なものと考えられていた。これを神と共に頂くという、いわば「神人共食」の感覚には、神と人々または人々同士の一体感を図り、神と共食することで神より授けられる生命力の更新、再生復活への願いが込められていたようである。
正月は神の力によって世の中の平安・家内安泰を祈る節目と考えられていた。初詣は、もともとは村の氏神様へ大晦日の夜からお籠りをしてその変わり目の加護を神に祈るためのものだったが、現在は除夜の鐘を合図に有名な神社や寺に参詣するのが一般的になっているようである。
本来、お正月は元日を中心とした大正月、15日の小正月、立春を中心とした正月の3度にわたって行われていたが、農耕社会の村ではいわゆる正月は2月1日であり、後正月は2月15日であった。終戦後、町との交流が深まるとともに、現代では正月は一律に1月1日となっている。
昔の感覚では、寒い冬ごもりから解放され春の到来を感じる立春の頃、つまり生命力が復活する春を迎えるときが正月であって、それを喜び合い祝うという発想が「めでたい」の語源であった。今も賀詞(がし)として「新春」「迎春」という言葉に当時の人たちの心意気が残されている。
正月を「めでたい」というのは、「正月様」という年神が家々を訪れて人々に祝福を授ける時季として「めでたい」のであろう。
正月が来ることで一斉に年を取るという「数え年」の感覚は、現在のように個人の誕生日ごとに年齢を加える「満年齢」の感覚と異なり、地区の同年齢のもの同士が相互につながりを持ちながら生活しようという連帯感、つまり「同齢感覚」を育んでいたようである。
来訪する年神様を大晦日から迎え正月との節目に供えたのが、おせち料理の由来と言われている。また、家の重要な場所などに供えられた鏡餅の飾りには、次のような意味が伝えられている。
・ダイダイ…代々の家が栄えるようにとの語呂合わせ。黄色い実(み)は翌年には緑になるので、再生復活への願いが込められていた。
・コンブ…一般にヨロコブに通ずる。古くは広布、夷子布と言われたところから恵比寿にかけた。
・ウラジロ…常緑のシダ類で裏が白いことから心が潔白とされ、白髪になるまでの長寿を願った。
・ユズリハ…新しい葉が成長して古い葉が落ちる様から、親から子へ代々ユズル形を示しているとされる。
・串柿…家族みんな仲良く、笑顔で健康に暮らせるようにとの願いを、2個(ニコニコ)ずつ、または6個(睦まじく)ずつという数にこめられている。 |
|
左義長


|
正月のしめくくりとして小正月にあたる1月15日前後の日曜日は、左義長と言われ、いわゆる「ドンド焼き」が今でも行われている。自治会や神社の世話役や壮年会の若い衆が総出で村の長老の指導を得てやぐらを組む。その材料となる稲ワラ集めは子供会の役目で、子どもたちが村の家々を回ってその日までにワラを集めておく。
やぐらを組むのは大抵松の内が明けた頃の日曜日(7日〜8日あたり)の初寄り合いの午後に行われた。この日は寒のうちで、例年降りしきる雪の中で行われるのが常で、半日かかってようやく完成する頃にはもう夕方になっている。午前中の初寄り合いの後で行われた鏡開きのぜんざいの残りを温めて、茶碗酒で冷え切った身体を温め合うひとときは、仲間意識や連帯感を覚える時であり、1年の折り目、節目を感ずるのもこんな時である。
ドンド焼きが行われるのは、その一週間後の日曜日である。神社の境内に組まれたやぐらの周りには、朝8時頃から村の家々から持ち寄られたしめ飾りなどの正月飾りをはじめ、習字や作文など処分したい子供の作品、1年間神棚などに祀られたお札など、ごみとして扱いにくいものが積み上げられ、神域でドンド焼きの聖なる火で燃やすことでけじめをつけた。
書初めをした用紙を左義長の火にくべて炎が高く燃え上がると書が上達するといって喜んだ。
赤々と燃え上がる炎を囲んで、老いも若きも男も女もひと時集うドンド焼きは、正月を締めくくる風物詩としてどこの地区の神社でも見られる年中行事といえよう。 |
|
湯の花神事
 |
白山神社(下中)の「湯の花神事」は毎年豊作を願って、5月15日と8月の第1日曜日に行われる。平成8年頃までは神事の時間帯は午後であった。しかし近年になってからは勤めに出る人が多くなり、日中の行事は困難になってきたため、現在は午前7時から実施されている。
この神事では、神主が境内で沸かされた鍋のお湯に米粒を入れ、来たる年も豊かに米の花が咲きますようにと祈願しお祓いをする。そのあと自治会長はじめ参加者が玉串の奉奠をする。
夏(8月)の神事では、地区の女子児童による巫女の舞いが神前で奉納される。
神社の建物は、昭和23年頃までは石の御堂のみだったが、その後境内の敷地を広め、昭和26年には御堂全体を囲う形で木造に建て替えられた。 |
|
西誓寺二十四日講
の思い出
|
年配の人には二十四日講は楽しい思い出としていつまでも記憶されている。二十四日講は、8月24日西誓寺にて執行され、沢山の「あきんど」が店(露店)を並べ、近在の子供たちが来て、好みのものを買って楽しんだ。
この二十四日講は、西誓寺の門徒の人達が本山護持のために西本願寺へ懇志をあげ、十二代目の准如上人よりご消息をいただいた。毎年講員が参集して正信偈のお勤めをして、一同お説教を聴聞し、秋の農作業への心の支えをいただいた。
境内では、子供たちが1年に1回の祭り気分を味わって遊びまわっていた |
|
片休み(野止め)
|
農家では春の彼岸から秋の彼岸までの毎月1日、7日、15日、23日は「片休み」と称され、午後の仕事を休むことになっていた。地区によっては多少日付が異なっていたが、その日はお寺で講が行われ、特に日ごろ家事で多忙な女性たちのための休みとも言われた。
当日は区長がそのことを太鼓で知らせ、それに違反したものは罰金として身欠き鰊(にしん)1束と酒2升を差し出さなければならなかった。また、「藁」をひっくり返したり、「肥」を撒いたりするような罰の地区もあったようである。その取締役的なことは青年会(15歳〜結婚するまでの若者)が行った。罰は農繁期における地域全体の連帯感を保つためのものであったが、現代ではこの風習は薄れつつある。 |
|