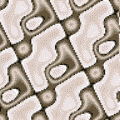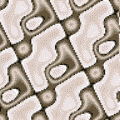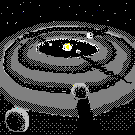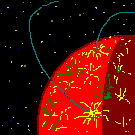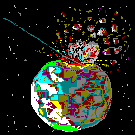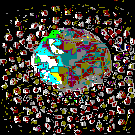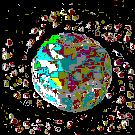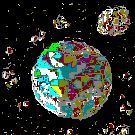飛び散った岩石はしだいに渦巻きをつくり、約1ヶ月ほどで全体質量の半分が1つの塊となり、地球の衛星=月が誕生した。誕生直後の月は、現在の距離の約1/16で、月は地球との潮汐作用でだんだん離れていったという。
海の誕生
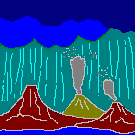
原始地球に微惑星が衝突するとその衝撃で高温・高圧になり、ガス化しやすい水や炭素化合物が蒸発し、大気がおおうようになった。
地球誕生から数億年が過ぎ、冷えて地表のマグマが固まると、大気中の水蒸気が一斉に雨となり「原始の海」ができる。
「二酸化炭素は海にとけ込み炭酸塩鉱物として堆積し、また火山ガスとして大気中に放出される。」という循環で、大気が安定する。
この頃の太陽は、現在より30%ほど暗かったという。しかし、高濃度の二酸化炭素による温室効果で地表は数十度の温度を保っていたと考えられている。太陽の輝きと呼応するかのように地表に大陸が出現し、CO2が大陸に堆積することでCO2濃度は少しずつ下がって行くことになる。
原始生命
始生代(46億年前〜38億年前)
 生命に必要な材料(アミノ酸)は降り注ぐ隕石によって供給されていた。
また猛毒物質に満ちた原始の海に、雷・宇宙線・紫外線・マグマの火山活動からの刺激でアミノ酸が生成される可能性もあった。
生命に必要な材料(アミノ酸)は降り注ぐ隕石によって供給されていた。
また猛毒物質に満ちた原始の海に、雷・宇宙線・紫外線・マグマの火山活動からの刺激でアミノ酸が生成される可能性もあった。
この頃、月は地球から分離したばかりで地球との距離も現在の半分ほどで、引力による潮の満ち干は激しく、原始の海は大きく攪拌されそのエネルギーが生命誕生の引き金になった。激しい波がつくる泡が保護膜となって、そのなかで原始生命の誕生という奇跡が起きた。
原始生命の正体ははっきりしていないが、生命の特徴
は次の4つ。
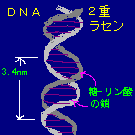
- 外界との区切り(細胞膜)、細胞構造がある
- 自己複製することができる
- 自己維持機能をもっている
- 進化する能力がある
生命誕生は2つの可能性が指摘されている。
●原始の海の中で作られたアミノ酸が変化したとする説。
- 自然発生のアミノ酸
1953年:大学院生であったS・L・ミラーは、原始地球の大気中と海と雷を再現するために、メタン、アンモニア、水素の混合気体、水を試験管の中に入れ繰り返し放電をし、内部の水を循環させた。数日後、密閉された試験管のなかから、いくつかのアミノ酸やその他の有機分子を確認したのである・・・。
- 集合タンパク質
模擬海水のなかにアミノ酸をいれて100゚Cで2〜3週間おくと、自然にアミノ酸の重合した小さな粒(マリグラヌールと呼んでいる)ができる。
最近「狂牛病」の原因であるプリオンというタンパク質が、核酸なしで自己増殖することが判明。プリオンと同じタンパク質はだれにもあるが、異常な型(プリオン型)が正常型に働きかけると、正常型が異常型に構造変化する。ちょうど触媒のような機能をもつタンパク質。
(「生命の地球」1998、三友社出版、柳川広志:三菱化学生命研究所室長)
- RNA(リボ核酸)ワールド
原始の海が冷えて、100゚C以下になると、RNAが自分自身で触媒作用するリボザイムというものが出来たとする説。RNAがどのように形成されたかは不明。
●地球外からもたらされたとする説。
- パンスペルミア説(RNA、DNAの飛来)
電解質理論で1903年ノーベル化学賞を受賞したアレニウス(スウェーデン)は、生命は宇宙のどこからか旅して地球に漂着したと考えた。微細な細菌や細胞胞子が、太陽風を受けて宇宙を旅する可能性を検討し、細胞胞子は約100km/秒の速度で旅してきたと計算した。(参考:2/Databook p93)
- 隕石飛来説
1969年、オーストラリア・メルボルン市北のマーチソンに隕石が落下した。隕石はアポロ計画の月の石分析用の実験室に運ばれ、アミノ酸など生体関連物質が何種類も含まれいることが判明した。後に、南極アランヒルズで見つかった隕石からもアミノ酸などが発見され注目された。(参考:2/Databook p94)
生命誕生星の条件
●太陽からの距離
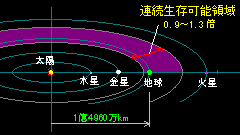 太陽系の9個の惑星のうち、地球だけに生命が誕生した理由を考えてみよう。まず9個の惑星の内似た惑星である金星・地球・火星を調べてみると、金星の表面温度460度C、火星は-60度Cに対して、地球は平均15度Cである。惑星の表面温度が地球のように温暖で、水が液体として存在するためには、惑星が受ける太陽エネルギィーが現在の地球の0.9倍〜1.3倍程度だと言われている。
太陽系の9個の惑星のうち、地球だけに生命が誕生した理由を考えてみよう。まず9個の惑星の内似た惑星である金星・地球・火星を調べてみると、金星の表面温度460度C、火星は-60度Cに対して、地球は平均15度Cである。惑星の表面温度が地球のように温暖で、水が液体として存在するためには、惑星が受ける太陽エネルギィーが現在の地球の0.9倍〜1.3倍程度だと言われている。
惑星が受ける太陽エネルギィーの量は、太陽の光度を一定とすれば、太陽と惑星の距離で決まる。惑星が生命生存に適した環境を持つ範囲を「連続生存可能領域」という。
●惑星の大きさ
- 惑星が小さい場合
惑星が小さすぎると惑星内部が早く冷え、火山活動が短く大気中に二酸化炭素を十分供給できないという。さらに、二酸化炭素の循環システムが働かず、大気を維持するために必要な重力が弱く、結局大気を失ってしまうのである。火星の質量は地球の1/10、地表重力は0.37倍しかない。
- 惑星が大きい場合
惑星が大きすぎると、強い重力で二酸化炭素や水蒸気が惑星表面に引き寄せられ、厚い大気を造る。この大気は、太陽光線は通過させるが地表の放射を邪魔する「温室効果」を発生させ、灼熱のガス惑星にする。
惑星が連続生存可能領域にあったとしても、惑星の大きさが適当でなければ生命を宿せない。ハート博士の計算では、質量が地球の0.85倍〜1.33倍が生命環境を維持できると範囲という。
●太陽(主星)の大きさ
生命が誕生しても、地球の例から推測すれば高等生物にまで進化するには30億年の時間が必要である。
星の寿命はその星の質量で決まる。質量が大きな星は燃料の消費速度も早く、寿命は短い。
惑星系を持つ有力候補として知られる画架座β星は、誕生してまだ10億年ほどであるが、質量が太陽の約2倍あるので寿命は15億〜20億年と推測されている。
惑星の主星(太陽)が死を迎えるとき、膨張を始める。惑星は膨張した星に飲み込まれ、灼熱の熱気と紫外線が降り注ぎ海は蒸発して、生物は全滅する。赤色巨星となった星は、周囲にガスや塵を吹き出しながら、ゆっくりと消えていく。最後に燃えかすの様な白色わい星がぽつんと残る。
ハート博士の計算によると、太陽の質量の1.2倍以上の星は寿命が30億年未満。一方、太陽の質量0.83倍以下の星は、その周囲に連続生存可能領域を維持するだけのエネルギィー放射がない。人間のような知的生命が住む惑星を持つためには、主星の質量が太陽の0.83倍〜1.2倍である事が条件となる。
▼参考文献
- NHK取材班著「生命40億年はるかな旅」1994、日本放送出版協会
- NHK取材班著「銀河宇宙オデッセイ」1990、日本放送出版協会

 Return Return
|