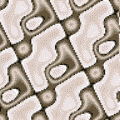
KenYaoの生命研究室
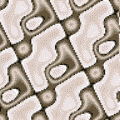
|
制作_2000年03月05日 更新*1_2021年07月21日 更新*2_2024年02月12日 生命研究史
進化の謎
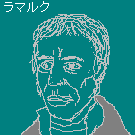 ラマルクは、その著書「動物哲学」1809年で「よく用いる器官は発達し、用いない器官は退化する。そしてこの形質が子孫に伝達されて、生物は進化する。」と述べている。これを用不用説と呼ぶ。 ラマルクは、その著書「動物哲学」1809年で「よく用いる器官は発達し、用いない器官は退化する。そしてこの形質が子孫に伝達されて、生物は進化する。」と述べている。これを用不用説と呼ぶ。しかし、生物が後天的に獲得した形質は遺伝しないことが明らかとなり、ラマルク説全体が省みられなくなった。 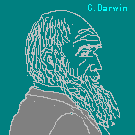 1809年、イギリス・シュルーズベリーの裕福な医者の家庭に生まれた。医学を学ぶためにエジンバラ大に入学。3年後、聖職者を目指してケンブリッジ・クライストカレッジに入学する。
1809年、イギリス・シュルーズベリーの裕福な医者の家庭に生まれた。医学を学ぶためにエジンバラ大に入学。3年後、聖職者を目指してケンブリッジ・クライストカレッジに入学する。1831年から5年間、調査船ビーグル号に乗って各地を調査。1839年「ビーグル号歴訪諸国の博物学及び地質学の研究日記」を出版。 ガラパゴス諸島で動物を観察から、生物進化の仕組み=自然選択説にたどり着いた。1859年「種の起源」出版。(参考2/p155~) 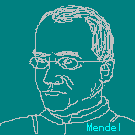 彼はブルノ(現在のチェコ)にあるトマス修道院の見習いとして、修道院長の作物の品種改良にを手伝うことから遺伝研究に入っていった。メンデルは6年間にわたりエンドウの交配実験を繰り返し、1865年ブルノ自然研究会で口頭で発表し、翌年その会誌に論文「雑種植物の研究」を発表した。
彼はブルノ(現在のチェコ)にあるトマス修道院の見習いとして、修道院長の作物の品種改良にを手伝うことから遺伝研究に入っていった。メンデルは6年間にわたりエンドウの交配実験を繰り返し、1865年ブルノ自然研究会で口頭で発表し、翌年その会誌に論文「雑種植物の研究」を発表した。メンデルはエンドウの7種の遺伝形質(種子の形が丸型orしわ型・・・他)を交配し、その雑種2世代まで調べることで、分離の法則・優勢の法則・独立の法則を発見した。(参考4/第一巻/P122) 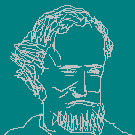 1900年前後ド・フリースはオオマツヨウグサの交雑実験で、カール・コレンス(独)、エリッヒ・チェルマク(オーストリア)は独自にエンドウの交雑実験でメンデルの法則を再確認した。(3人はほぼ同時に、35年前のメンデルの論文を発見した。)
1900年前後ド・フリースはオオマツヨウグサの交雑実験で、カール・コレンス(独)、エリッヒ・チェルマク(オーストリア)は独自にエンドウの交雑実験でメンデルの法則を再確認した。(3人はほぼ同時に、35年前のメンデルの論文を発見した。)また、オオマツヨイグサで突然変異を発見したド・フリースは「進化の基となる変異は突然変異で生じ、それに自然選択が働く」と考えた。 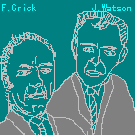 クリックは1932年ユニバ-シティ・カレッジ・ロンドンに入学し物理学を専攻する。1949年、ケンブリッジ大のキャベンディシュ研究所に入り、X線結晶回析を研究。
クリックは1932年ユニバ-シティ・カレッジ・ロンドンに入学し物理学を専攻する。1949年、ケンブリッジ大のキャベンディシュ研究所に入り、X線結晶回析を研究。
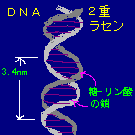 ワトソンは、1943年15歳でシカゴ大学に入学。動物学を研究する。インディアナ大で博士号を取得後、コペンハーゲンに研究留学する。1951年、キャベンディシュ研究所に移り、クリックと共同研究を開始する。
ワトソンは、1943年15歳でシカゴ大学に入学。動物学を研究する。インディアナ大で博士号を取得後、コペンハーゲンに研究留学する。1951年、キャベンディシュ研究所に移り、クリックと共同研究を開始する。1953年、春のある土曜の午前中、ワトソンはねじれた縄ばしごのような構造を見つけた。クリックとワトソンはDNAの構造と機能に関する4つの論文を発表する。(参考2:p301~) 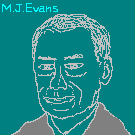 1981年英国ケンブリッジ大学のマーティン・エバンス博士らが、マウスの胚盤胞からES細胞(多能性幹細胞の一つで、あらゆる組織の細胞に分化できる)の生成に成功する。
1981年英国ケンブリッジ大学のマーティン・エバンス博士らが、マウスの胚盤胞からES細胞(多能性幹細胞の一つで、あらゆる組織の細胞に分化できる)の生成に成功する。その後、1998年米国ウィスコンシン大学のジェームズ・トムソン教授が、ヒトES細胞の生成に成功。 ヒトES細胞(受精後6,7日目の胚盤胞から細胞を取り出し、それを培養して生成する)を使い、人間のあらゆる臓器の細胞を作る出すことで、難治性疾患の細胞移植治療などの再生医療への道が開くと期待される。(参考5) 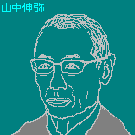 山中教授は奈良先端科学技術大学院大学の助教授であった2000年ころからES細胞の遺伝子に関心を持ち、新しい多能性幹細胞の制作方法の研究に取り組む。
山中教授は奈良先端科学技術大学院大学の助教授であった2000年ころからES細胞の遺伝子に関心を持ち、新しい多能性幹細胞の制作方法の研究に取り組む。2006年、数多くの遺伝子の中から、ES細胞で特徴的に働く4つの遺伝子(Oct3/4、Sox2、Klf4、C-Myc)を見出し、レトロウイルス・ベクターを使ってマウスの皮膚細胞に導入し、数週間培養しました。送り込まれた4つの遺伝子の働きにより、リプログラミングが起き、ES細胞に似た多能性幹細胞が出来ました。マウスiPS細胞の誕生です。 2007年11月、工夫を重ね4つの遺伝子を人間の皮膚細胞に導入して、ヒトiPS細胞の生成に成功し発表する。2012年ノーベル生物学医学賞を受賞。再生医療の臨床研究に取り組む。 (参考5) 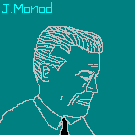 最初にmRNA(メッセンジャーRNA)の存在を指摘したのは、フランスの生物学者ジャック・モノーとフランソワ・ジャコブです。1965年、2人はノーベル生理学医学賞を受賞。その後、米の遺伝生物学者マシュー・メルセンが、mRNAの存在を実証しました。
最初にmRNA(メッセンジャーRNA)の存在を指摘したのは、フランスの生物学者ジャック・モノーとフランソワ・ジャコブです。1965年、2人はノーベル生理学医学賞を受賞。その後、米の遺伝生物学者マシュー・メルセンが、mRNAの存在を実証しました。DNAに書かれた情報がmRNAを介してタンパク質の合成に至る、という分子レベルの仕組みが解明されました。 (参考6) 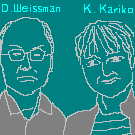 ハンガリー出身のカタリン・カリコ氏は、自国の大学でmRNAの発見に感動して生物学の研究者となる。地元で研究員となるが研究資金が打切られ、1985年夫と子供の3人で渡米する。
ハンガリー出身のカタリン・カリコ氏は、自国の大学でmRNAの発見に感動して生物学の研究者となる。地元で研究員となるが研究資金が打切られ、1985年夫と子供の3人で渡米する。フィラデルフィアにあるテンプル大学の研究員、4年後ペンシルベニア大学の助手となり、mRNAの研究に没頭した。しかし当時はmRNAをただ生物に投与しても、免疫によって異物として除かれ、実用化が進まなかった。 1997年偶然の出会いがカリコ氏を助けます。ペンシルベニヤ大学に着任したドリュー・ワイズマン教授はHIVワクチン開発を目指していました。コピー機の前で出会った2人は、mRNAを使った共同研究が始まります。 そして「mRNAの構成物質「ウリジン」を改変すると、免疫による炎症反応を抑えられる」とする論文を2005年に発表する。 2008年には、特定の「シュードウリジン」に置き換えることで、目的たんぱく質作成の効率が劇的に上がると発表する。DNAを使ったワクチン開発が行き詰まる中、mRNAによるワクチン開発の道が見えてきましが、この時点でこの発見の重要性は見逃されていました。 (参考6) ▼参考文献
 Return Return
|