![]()
さて、「騎士」になるためには一体どうすれば良いのでしょう、そしてどんな人がなれるのでしょう。
現代では、イギリス王室から「ナイトの称号」を与えられた人はもちろんの事・・・・
フランスのヴジョにはワイン騎士団とかいうものもあるそうですね。でも、特にそういった資格を得ずとも、
「私は騎士だ」と思ったり名乗ったりすれば、それはもう立派な騎士になれるのだと思います(笑)
そして後にも扱いますが、「騎士道精神」に沿って行動しようとする人も、騎士でいいのだと私は勝手に思っています。
戦えないから騎士にはなれない、身分が低いからなれない・・・とか言う、中世とは違うでしょう。
残念ながら中世では、騎士は誰でもなれるものではありません。
騎士は戦士だ、と「騎士とは何か?」のページで触れましたが、農民が戦士になっても「騎士」
と世の中で認められることは決して御座いません・・・・。哀しいですがそれは「ただの戦士」でしかないのです。

騎士は「貴族」です。貴族の子供が騎士になるための教育を受け、なおかつ、「騎士叙任式」で
叙任された時初めて、騎士としての人生が始まるのです。
当時は、子供が7歳くらいになると、将来に備えた職業教育を受けさせるようでした。(身分に関わらず)
貴族の子供は、騎士になる者は騎士の教育、聖職者になる者は聖職者の教育を受けます。
(女性の騎士は、残念ながらほとんど?と言うか全く見かけません。ですが有名な所では、フランスの
聖少女ジャンヌ・ダルク
がいますね。異例ですが、男性のように騎士として戦い・・・。)
で、騎士になる子供が受ける教育と言えば、やはり「武芸」、「戦闘」が中心でした。
とは言え、諸侯や城主など、高位の貴族(騎士)の子供は、その武芸だけでなく修道院にも入れられて、
学芸も教えられます。ラテン語を堪能に操れるようにとか、文武両道といったところでしょうか。
とにかく騎士になる子供は、主に戦闘に関する知識、実技を叩き込まれます。
![]()
STEPⅠ
馬と言う動物を理解し、馬に乗る練習を始めます。
剣(sword,ソード)を振るう練習も始めます。
軍事演習である狩猟にも連れて行ってもらいます。
実技訓練も開始されますが、それは今の軍隊?のように考え抜かれたものではなく、
ひたすら剣を交わして勘を磨くのでした。重い剣を振るうのだから、力だけが大事かと思えば
そうではありません。いかにすばやく振るかと言う事がトレビアンにつながるのでした。(笑)
「重い一撃」よりは、「素早い多くの手数」の方がより効率的なのでした。
剣は初めの内は木剣を使い、慣れたら鉄の剣に変えていったそうです。
騎士の子供であれば、子供時代の「外での遊び」として戦いの真似事(戦争ごっこ)をしていたでしょう。
木剣は使い慣れたオモチャと言った所でしょうか。おままごとをしていては騎士になりにくいでしょうね。(笑)
しかし、さすがに木剣と真剣は違います。まずは、真剣で自分を傷付けないようにする事から始まりました。
![]()
STEPⅡ
剣と同じくらい重要なのが、騎槍(lance,ランス)です。
騎槍は、剣に並ぶ主要武器であり、また騎士たちの名誉と武技の見せ所でもある
「トーナメント(馬上試合)・・・(他で扱います)」に関わることでもあったので欠かせませんでした。
日本の歴史大河ドラマでは、サムライが槍を頭上で回転させたりしますが、西欧中世騎士は致しません(笑)
騎士たちは馬上で長い騎槍を脇に抱え、馬を直線的に走らせ、勢いに乗せて
騎槍の先端にある穂先を相手(敵対者)の胸に当てます。
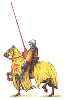
こうした騎槍の練習には、quintain(クィンティン,英)、quintaine(カンタン,仏)と呼ばれる
案山子のような道具が使われたと言う事です。カカシと聞いて思い出すのは、オズの魔法使いに出てくる、
脳みそを欲しがる案山子です。何と和やかな話でしょう(笑)
しかし此処での案山子はそんな和やかで可愛らしいものでは御座いません・・・・
単純なものは、地面に埋め込んだ垂直の棒に横棒を付け、小さな輪の的を先端に付けた短い棒を
横棒に通したものです。標的の輪を綺麗に突けば、輪のついた棒は横棒を中心に縦に回転しました。
他にも、短剣、弓、棍棒類など、色んな武器について学びます。ひととおりは触れるはずです。
実際に自分が使わなくても、その武器の特性などを理解し、それらの危険性をも熟知できれば
それに越したことはないでしょう。
さて、それらで経験を積んだ後、これからが本番です。
騎士修行は、後編へ続きます^^