配管(水道等)における栓に相当する
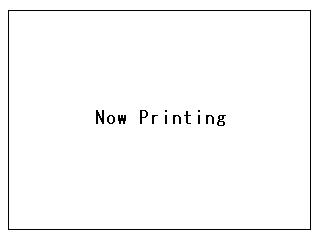
主な材料は厚さ1.2~1.6㎜の鋼板。
外形は接続されるダクトと同じく丸型/角型の物がある。
内部には流れをを弱くさせる為の羽根があり、これ開閉する事で風量の調節を行う様に作られている。
形状や目的等に応じて羽根の枚数や動き方が異なる。
細やかな風量調節を行う場合には”対向翼”、全開/全閉しか行わない場合や確実に気流を止めたい場合には”平行翼”といわれる、羽根の動きをするダンパーが使用される。
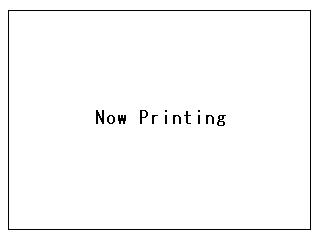
略称VD (Volume Damper)
文字通り、風量調節を行うダンパー。
過大な風量の抑制を必要とする部分に使用される。
特徴は細やかな調節が出来る事。
蛇口の栓と同様に、ハンドルを左右に回す事で羽根が動き風量の制御を行う事が出来る。
手動で制御を行う様に作られているので、自動で風量調節を行う事は出来ない。
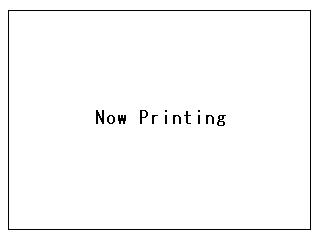
略称MD (Motor Damper)
無人状態で空調機器の制御装置が開閉を行なえる様にするため使用されるダンパー。
羽根の開閉をモーターで行う。
基本的には全開/全閉のどちらかとなり、細やかな風量調節は出来ない。
主に空調機の外気取入(OA)制御の為に使用される。
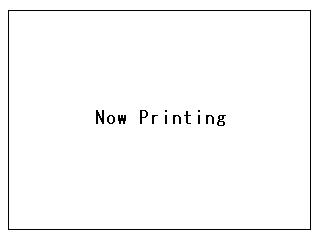
略称CD (Chuck Damper)
逆流を防ぐ為のダンパー。
排出しようとする気体が、外部で発生する風などが原因で元に戻ろうとする事を防ぐのが目的。
主に空調機や送風機の外部排気(EA)部分に使用される。
類似する物として、換気扇に取付けられる風圧シャッターなどがある。
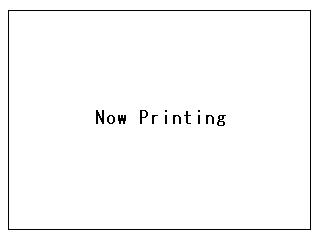
略称FD (Fire Damper)
ダクト内に高温度の気体や炎そのものが通過した時、即座にダクトを遮断。
これにより、火災発生地点からダクトを通じての延焼が起こる事を防ぐのが目的。
ダンパー内部には温度ヒューズが取付けられており、これが熱で溶け切れた時はスプリングの力でダンパーの羽根が閉じられる。
環境によって、72℃(一般)/120℃(厨房排気)/280℃(排煙)のヒューズが使用される。
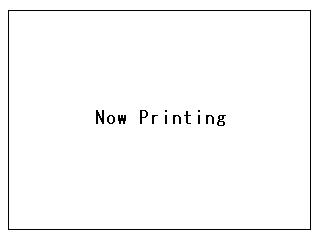
略称SD (Smoke Damper)
火災発生地点からダクトを通じて、他の空間(上層階など)へ煙が流出する事を防ぐのが目的。
独自で動作する防火ダンパーとは違い、火災報知器や煙感知器の反応により防火装置が発生する電気信号/ワイヤーを通じての手動操作により、ダンパーの羽根が閉じられる。
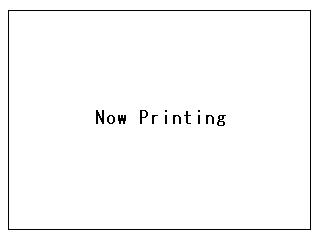
略称PD (Piston Damper)
消火用ガスがダクトを通じて漏れる事により消化効率が落ちる事を防ぐのが目的。
スプリングで羽根の閉鎖を行う防火ダンパーとは違い、消化用ガス(CO2等)の配管をダンパーの駆動部分に接続、火災が発生した時に消化用ガスを噴出させる為の圧力を利用してダンパーの羽根を閉じる物。
ガス圧作動ダンパー(GD)とも呼ばれる。
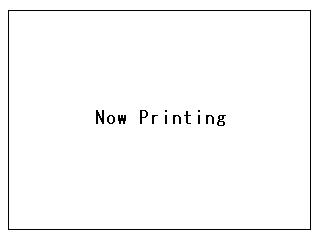
略称VAV (Variable Air Volume)
広い意味でダンパーと言ってよいと思われる。
センサー(サーモスタット)からの情報により羽根の開閉をモーターで行い、細やかな風量調節を行う物。
室内の負荷(温度差)が大きい場合には風量を多くし、負荷が小さくなる(目的の温度に近づく)につれて徐々に風量を少なくする。
これにより空調機の負担を軽減する事が出来、運転費用(ランニングコスト)の低減などが可能となる。
VAVにも色々あり、上で説明している物は”絞り型”と呼ばれます。
また、定風量ユニット(CAV:Constant Air Volume)という物もある。
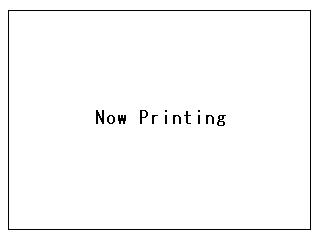
防火ダンパーと風量調節ダンパーを兼ね備えた風量調節型防火ダンパー(FVD)、
防火ダンパーと防煙ダンパーを兼ね備えた防火防煙ダンパー(SFD)、
防火ダンパーと防煙ダンパー、さらに風量調節ダンパーを兼ね備えた防火防煙風量調節ダンパー(SFVD)などがある。