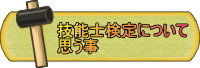
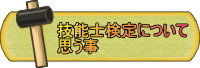
○技能士について(要約: 各所から引用)
![]()
技能検定は、「働く人々の有する技能を一定の基準により検定し、
国として証明する技能の国家検定制度」です。
職業能力開発協会が行う技能検定に合格した者に送られます。
合格者には厚生労働大臣名(特級、1級及び単一等級)
又は都道府県知事名(2級、3級、基礎級)の
合格証書が交付され「技能士」と称することができます。
技能検定は、労働者の技能の程度を検定し、国が技能を公証することで労働者の
技能習得意欲を増進し、技能に対する社会一般の評価を高め、
労働者の技能と地位の向上を図るものです
※昨年度までは、労働大臣名による交付でした。(今は省庁再編)
建築板金(ダクト板金)の場合、1級と2級があります。
○実技試験
![]()
 ← 1級の課題です
← 1級の課題です
実技試験では、上のダクトを規定時間内で製作する事を求められます。
そして全て手作業で行います。
ハンマーなどの工具は使用しますが、機械は一切使用できません。
また、4時間以内で完成/提出できなければ失格となります。
※数ヶ月前に課題内容(第三角法で書かれた完成図)が送付され、
試験当日までの間、各自で練習を行います。
実際はこの間、受検者を集めて講習会が行われます。(地域によるらしい)
試験会場は「技能検定受検表」で指定された場所で行われます。
私の場合は、県の板金学校(職業能力開発校ではない)でした。
この試験では、以下のような事を要求されます。
いずれも「機械は使用しないで」行わなくてはなりません。
また、「ただ形にすればよい」というものでもありません。
そして、受検者の「態度」も考慮されるようです。
順序はこの様になります。
結果は数ヵ月後に通知されます。
実技試験は合格したが、その後に行われる学科試験が駄目だった場合ですが、
再度、技能試験を受ける場合には実技試験は免除されます。
(学科試験だけを受ければよい)
○学科試験
![]()
学科試験は、真偽法(○×法)で行われます。
実技試験の場合と同様、事前に講習会などで問題集をこなしておきます。
(ちなみに雇用問題研究会と言う所から、問題集が発刊されていたりします)
実技と同様、「技能検定受検表」で指定の場所でペーパー試験を受けます。
出題数は60〜100で、試験時間は2時間です
この様な問題が出ます。
○×法なので解る問題は確実に解いて、よく解らないものは勘で済ませます。
ちなみに、数年前までは「減点法」なる物が採られていました。(現在は行われていません)
※間違った答えが書いてあった場合、減点対象となります。
(全100問で、80問正解で合格であった場合を例にしてみます)
85問は正解しているのに残り15問を適当に書いて、その15問がすべて間違いだった場合、
85 - 15 = 70点になってしまい、失格になってしまいます。
そのため、80問以上正解確実と思った場合は、残りの答えを「わざと」書かないで
提出する事を教えられました。
結果は数ヵ月後に通知されます。
学科試験は合格したが、その前にに行われた実技試験が駄目だった場合ですが、
再度、技能試験を受ける場合には学科試験は免除されます。
(実技試験だけを受ければよい)
○私が思う事
![]()
別にこれに合格できなくてもダクトは作れます。
別にこれに合格できなくてもダクトは吊れます。
1人の作業員として必ずしも必要では無いと思われます。
他のダクト会社では、「受けさせる必要は無い」と言っている社長もいるようです。
(プラズマ切断機/成形機全盛の今では、ある意味間違いではないでしょう)
では、なぜこの試験を受ける社員がいる/受けさせる会社があるのでしょう。
一つは会社/社員の技術レベルを他に示す事が出来るから。
一つは技能士がいないと仕事をさせてもらえない現場があるため。
一つは努力をする事で社員の技術がアップするから。
一つは、合格できた事で社員に自信がつく。
私が思いつくのはこれくらいです。
あ、もう一つ思いつく事がありました。
プラズマ切断機では切れない/成形機では曲げられない、
機械では作る事の出来ないダクトを作る事が出来る
という事です。
現在では、この様な「全て手作業で作らなくてはならないダクト」を
なるべく必要としない様に設計がされています。
(一日数本しか製作できないのでダクトの値段が高くなってしまうなどの理由から)
でも出てくるんですよね、場合によっては。
その時に作れる人がいるかいないかで、その会社の技術レベルが計り知れます。
結局私が言いたい事なのですが、
「受ける必要は無い/受けるのが面倒」と思われる方は、受けなくてもよいでしょう。
※上にも書きましたが、必ずしも必要な物では無いのですから。
でも、「自分の実力を試してみたい/自分の実力を他人に示したい」と
思われる方は、受けてみましょう。
何かが変わりますよ。(言葉では言い表せませんが...)
![]()