|
1997/10/5作製
2006/1/12更新
天動説から地動説へ
コペルニクス
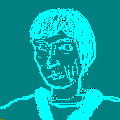 ○生涯(1473-1543年)
○生涯(1473-1543年)
- 職 業:天文学者、司教区行政官
- 出生地:ポーランドの商都トルニ
- 活動地:ポーランド
- コペルニクスの生涯
●コペルニクスの地動説
コペルニクスが「地球を動かす」決断をするにいたったのは、プトレマイオスの周転円説
の修正がきっかけだった。地球を中心とした火星天球と太陽天球が交差することに不合理を感じたのである。
天球モデルといっても数学的な概念ではなく、何らかの物質的な体系である以上、天球が相互に交差浸透(衝突)することになるからである。
彼は伝統的な天球モデルと一様円運動の遵守から、思いがけなく地球の公転運動に行き着いた。
地球に公転運動を与え、さらに自転運動・歳差運動(自転軸のふらつき)を採用した。また太陽中心の惑星配列の再構築で、惑星の逆行を説明した。
(逆行現象を完全に解消するには、ケプラーの楕円軌道説を待たなければならない)
彼の太陽中心説の革新性は、その宇宙観にも現れる。地球が動くとなると恒星の年周視差が存在することになるが、
それは当時の技術では観測されなかった。彼は伝統的な恒星天球にの大きさにも変更を加え、はるかに巨大なものであると主張した。
ただし、それが有限か無限かは態度を保留している。
ティホ・ブラーエ
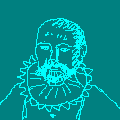 ○生涯(1546-1601年)
○生涯(1546-1601年)
- 職 業:天文学者、ロスギルドの司教
- 出生地:デンマーク
- 活動地:スウェーデン領フーヴェン島(デンマーク王が借用)
●ブラーエの仕事
おそらく個人の趣味(純粋に科学的な探求心)から、本格的な天体観測装置を作った最初の人です。
彼は貴族の息子で、若い頃各地を見学して回りました。特にドイツで見たカッセル天文台は、
世界で初めて半休のドームを回転させる屋根を持つ精密天体観測所で、心を引かれたようです。
1571年、ティホは伯父の居城内に天文台を建ててもらい観測を始めました。
1572年11月11日、居城内の観測所でカシオペア座に金星ほどもある明るい星を見つけました。
これは近年になって「超新星」と判定さ、現時超新星残骸(SNR)として「G120.1+1.4」と命名されています。
1576年デンマーク王に才能を見込まれ、フーヴェン島の天文台用地と年金支給を受け、
彼はここにウラニボリ天文台を建設して観測を続けました。
この天文台にはドームを持った観測所のほかに、図書館・実験室・印刷所・住居・観測機械工場が
付属し最高水準の天文台でしたが、望遠鏡が登場するのはまだ30年ほど先です。
彼の作った観測機器はいずれも精密で、観測データーは肉眼によるものとしては大変優れていました。
とりわけ彼の惑星観測は規則的に積み重ねられ、貴重なデーターとしてケプラーに受け継がれました。
ガリレオ・ガリレイ
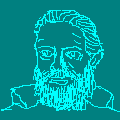 ○生涯(1564-1642年)
○生涯(1564-1642年)
- 職 業:天文学者
- 出生地:イタリア:ピサ
- 活動地:パドゥバ→フィレンツェ(イタリア)
●ガリレオの望遠鏡
ピサに生まれたガリレオは、25歳でピサ大学の数学講師となる。
このころからガリレオはメジチ家のコシモ公と親密となり、物心両面で援助を受けました。
1591年に父の死去後、コシモの口添えでヴェネチア共和国の招きを得て、パドゥバ大学の数学教授
(1592年〜1610年)となりました。
1609年、オランダで望遠鏡が発明された話を聞き、ガリレオはその原理を推理して自分で望遠鏡をつくることに成功しました。
その年の夏、ヴェネチアの高官や貴族に望遠鏡の観測会を実演して、年俸を得ました。
ある時ローマ法王の招きで講演会を開き、望遠鏡で観測した月のクレーターや木星の4惑星発見の話をしました。
講演の最後に「コペルニクスの地動説」の正当性を主張したので、評判になりガリレオの名前は全ヨーロッパに知れ渡るようになりました。
●異端者ガリレオ
ガリレオは有名になった反面、彼の地動説に反対する者も現れフィレンツエに移りました。
金星の満ち欠け、太陽黒点の発見などの成果をあげましたが、同じ頃独立に発見した他人との先取権争いをして、
さらに敵を増やす結果になりました。
1615年ガリレオは異端者として告発され、法王より「地動説の放棄」を命ぜられました。
1632年地動説に基づいた天文書を出版したため、1633年再度告発され今度はフィレンツェ郊外の山荘に軟禁されました。
ヨハネス・ケプラー
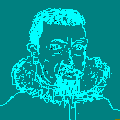 ○生涯(1571-1630年)
○生涯(1571-1630年)
- 職 業:天文学者
- 出生地:ドイツ・シュツッツガルト近郊
- 活動地:グラーツ→プラハ→リンツ→ウルム
●惑星の運動法則
ケプラーは喧嘩の絶えない家庭環境で育ちましたが、地元貴族の援助を受けてチュービンゲン大学卒業後、
オーストリアのグラーツで教師になりました。その地で貴族の娘と結婚して、家庭をもちました。
教師をしながらグラーツ町の暦作りに関わり、占星術を使った予言で評判を得るようになりました。
彼は暦作りがきっかけで天文学に興味をもち、宇宙は幾何学的原理に支配されていると信じるようになる。
太陽と各惑星との間には、立方体や球などの架空の立体があてはまるという理論「宇宙の神秘」と題する本を発表し、
それがデンマークの天文学者ティホ・ブラーエの目に止まる。(参考文献5)
ティホ・ブラーエは1599年ドイツのルドルフ2世に招かれ、プラハのベナツキー城に観測場所を移しました。
その直後、ケプラーは文通していたティホの助手になり、2年間共に研究をしました。
1601年ティホが急死したあと、彼は火星の観測をはじめました。長年に渡るティホの観測記録を受け継ぎ、
10年ほどの間に惑星の運動法則を見つけました。
- 第一法則:惑星は太陽を焦点とする楕円軌道を公転する。
- 第二法則:惑星と太陽を結ぶ線が等しい時間に作る軌跡面積は等しい。
- 第三法則:惑星の公転時間の2乗は太陽からの平均距離の3乗に比例する。
1612年ルドルフ2世が没するとケプラーは援助打ち切られ、リンツに移りました。
リンツで自分の発見した3法則を使って計算し、1625年新しい惑星表「ルドルフ表」をつくりしました。
30年戦争のため出版が遅れ、1627年ウルムに移ってようやく出版されました。
この表は惑星位置推算表として100年以上にわたって世界中で使われました。
▼参考文献
- トーマス・クーン著「コペルニクス革命」1989(常石敬一訳)、講談社学術文庫
- ティモシー・フェリス著「銀河の時代」1992(野本陽代訳)、工作舎
- コペルニクス(高橋憲一訳・解説)「コペルニクス・天球回転論」1993、みすず書房
- 吉田正太郎著「望遠鏡発達史」1994、誠文堂新光社
- ジョージ・G・スピーロ著「ケプラー予想」2003(青木薫訳2005)、新潮社
 Return Return
|
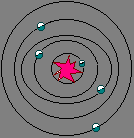
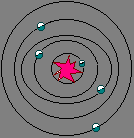
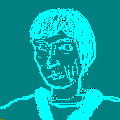 ○生涯(1473-1543年)
○生涯(1473-1543年)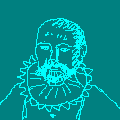 ○生涯(1546-1601年)
○生涯(1546-1601年)